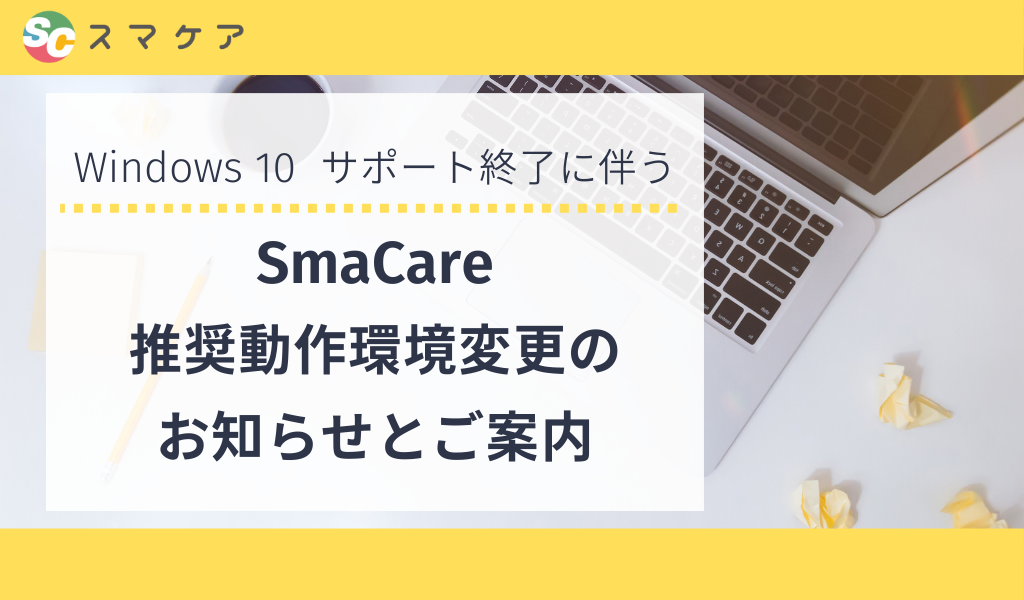
【Windows10サポート終了】SmaCare推奨動作環境変更のお知らせとご案内

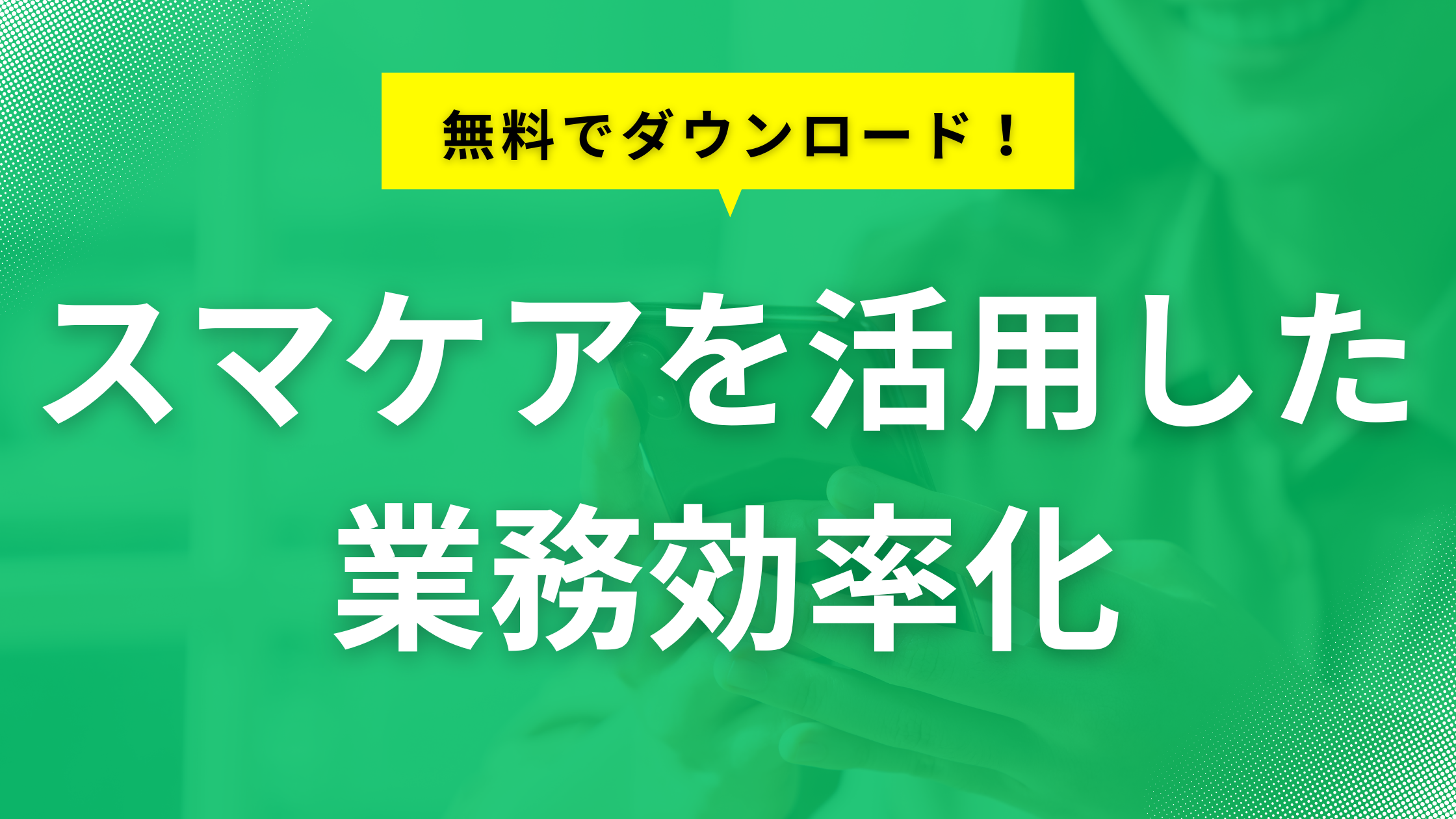
令和7年8月15日、厚生労働省より、高齢者に対する熱中症予防のための見守り・声かけの強化について事務連絡が出されました。
政府では、「熱中症対策実行計画」(令和5年5月30日閣議決定)に基づき、令和7年度「熱中症予防強化キャンペーン」を通じて普及啓発を実施しておりますが、
特に高齢者においては、自ら熱中症予防行動をとることが難しい場合があり、厚生労働省の資料でも、熱中症による救急搬送者や死亡者の多くが高齢者であることが指摘されています 。
本記事では、厚生労働省の資料を参考に、高齢者が熱中症になりやすい理由と、介護事業所が取り組むべき具体的な対策、そして業務効率化を通じて質の高い見守りを実現する方法について解説します。
参考資料:熱中症対策のための高齢者への見守り・声かけについて (事務連絡 令和7年8月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001540305.pdf
高齢者が熱中症になりやすいのは、以下のような身体的な特性があるためです。
◆暑さを感じにくい
└ 感覚が鈍り、「暑い」と感じにくくなります。
◆体内の水分量が減少
└ もともと体内の水分量が少ない上に、喉の渇きも感じにくくなります。
◆発汗・皮膚血流量の遅れ
└ 体温を下げるための発汗や皮膚の血流量の増加が遅れ、体内の熱をうまく逃がせません。
これらの特性から、高齢者への熱中症予防の呼びかけや見守りが特に重要になります。
2.介護事業者ができる熱中症予防と見守りのポイント
政府は、「熱中症対策実行計画」に基づき、国民や消費者、そして事業者に対して熱中症対策への協力を求めています。
高齢者を見守る立場として、以下の点に取り組むことが大切です。
◆こまめな声かけ
└ 「喉が渇かなくても早めに水分・塩分を補給しましょう」と声をかけ、定期的な水分補給を促します。
<厚労省 呼びかけ例>
・のどが渇かなくても、早め早めに水分や塩分を補給しましょう。
・エアコンを積極的に使用しましょう。その際、直接肌に風が当たらないようにしましょう。
◆室温管理の徹底
└ WBGT計や温湿度計を用いて、室内の温度を適切に保つよう支援しましょう。
◆体調や環境の確認
└ 元気があるか、食欲はあるか、部屋の温度や風通しは適切かなどをこまめに確認し、サポートします。
利用者様の安全を守るためには、スタッフが利用者様と向き合う時間を十分に確保することが不可欠です。
しかし、日々の記録業務や事務作業に追われ、思うように見守りの時間を確保できないこともあるかもしれません。
そこで、ICTの活用による業務効率化が鍵となります。
定期巡回・随時対応サービス業務支援システム「スマケア」は、日々の記録業務をスマートフォンなどでデジタル化し、スタッフ間の情報共有をリアルタイムで行うことができます。
これにより、事務作業の負担を大幅に軽減し、スタッフはより質の高いケアや見守りに集中できる環境を整えることができます。
熱中症対策は、利用者様の命を守る上で欠かせない取り組みです。
業務を効率化し、スタッフが見守りに専念できる環境を整えることは、利用者様の安全だけでなく、事業所のサービスの質向上にも繋がります。
「スマケア」は、業務支援システムとして日々の業務を効率化するだけでなく、これから定期巡回事業を立ち上げたい事業者様のサポートも行っています。
この夏、熱中症対策を強化し、安心・安全なケアを提供したい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ご興味のある方は、お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡をお待ちしております。