
【2026年6月処遇改善加算改定】定期巡回サービスが「加算率27.8%」を勝ち取る方法

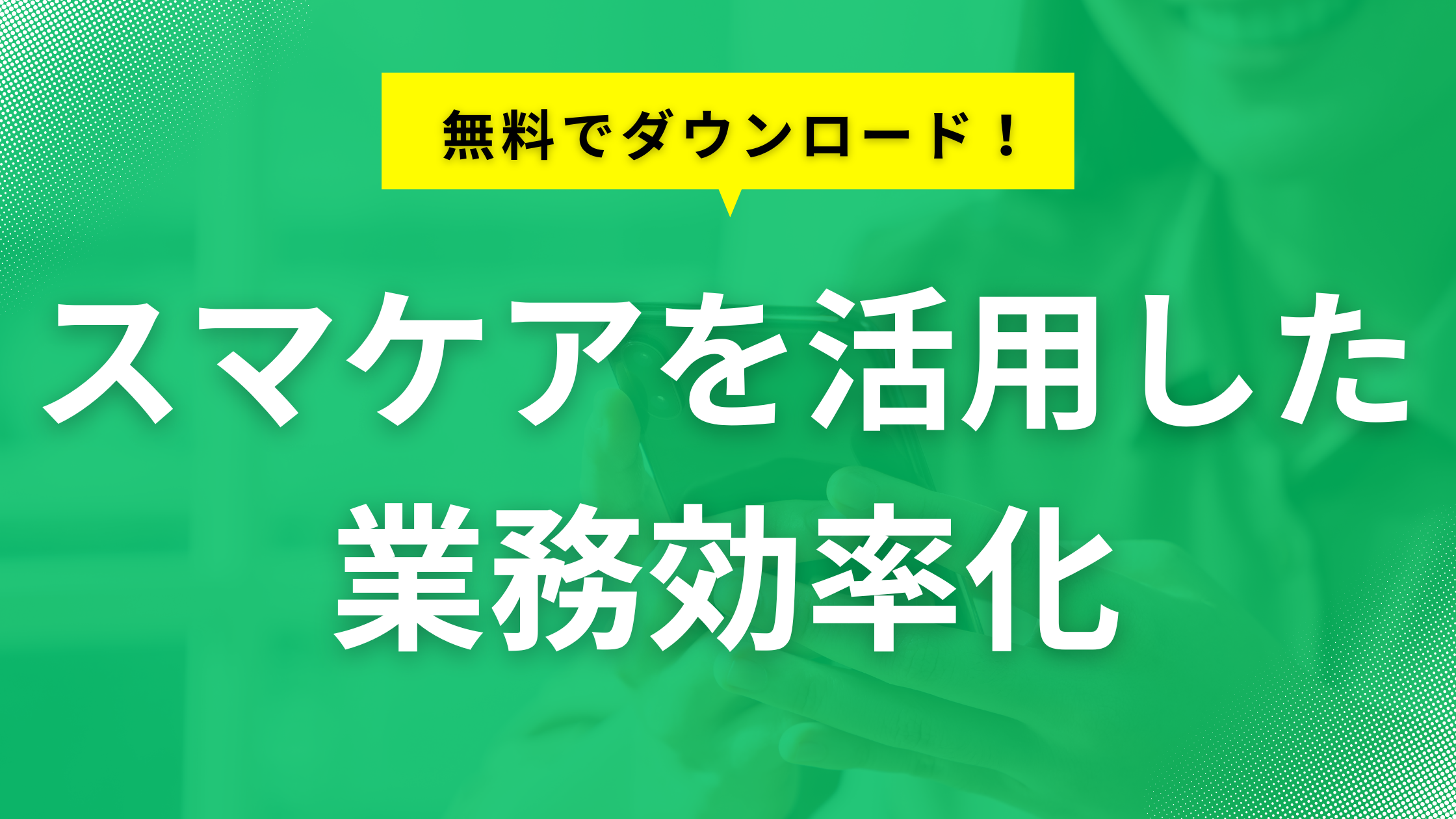
「もし、あと一日早く訪問していれば…」 介護の現場で、そんな風に胸が痛んだ経験はありませんか?
日々の業務に追われる中で、利用者様の小さな変化に気づき、その暮らしを支えたいと願う一方で、サービスの合間に何か起きていないだろうか、と不安に感じる瞬間もあるかもしれません。
先日、警察庁から非常に衝撃的なデータが発表されました。
今年(令和7年)のわずか半年間で、3万人を超える65歳以上の方々が、ご自宅で誰にも看取られることなく亡くなっていたというのです。
この数字には、もちろん介護サービスを利用していなかった方も多く含まれるでしょう。
しかし、在宅での生活に何らかの不安を抱え、支援を必要としていた方がいた可能性は否定できません。
そして、こうした「静かなSOS」にいち早く気づき、手を差し伸べることができるのが、地域に根差した私たち介護事業者ではないでしょうか。
この数字を「これから私たちが救えるはずの命の数」と捉え、何ができるのかを一緒に考えていきたいと思います。
まずは、私たちが向き合うべき現実を、具体的な数字で見ていきましょう。
大切なポイントを3つに絞ってご紹介します。
数字1:亡くなった方の「77%」が65歳以上
ご自宅で一人で亡くなられた方のうち、実に4人に3人以上が高齢者という現実があります。
特に75歳以上の方が多く、後期高齢者の方々の暮らしをどう支えるかが、いかに大きな課題であるかがわかります。
これは、私たちが日々接している利用者様が、まさにその中心にいらっしゃることを示しています。
数字2:「8,353人」の発見が8日以上遅れている
さらに深刻なのは、発見されるまでの時間です。
一般的に「孤立死」の目安ともいわれる、亡くなってから8日以上経って発見された高齢者の方が、この半年だけで8,353人もいらっしゃいました。
中には、1ヶ月以上経ってから見つかった方も2,800人以上います。
ご本人やご家族の無念を思うと、本当に胸が痛みます。
数字3:現役世代も「23%」
この問題は、高齢者の方だけの話ではありません。
亡くなられた方のうち、約4人に1人は65歳未満の現役世代でした。
病気や社会からの孤立など、様々な背景が考えられますが、年齢を問わず、いかに地域社会とのつながりが薄れている人が増えているかの表れかもしれません。
これらの数字は、単なる統計データではありません。
その一つひとつが、誰かの大切な人生の結末です。
そして、この状況を変える鍵を、私たち介護事業者が握っているのかもしれません。
2.なぜ発見が遅れてしまうのか?従来の在宅介護サービスが抱える限界
では、なぜこれほど多くの方の発見が遅れてしまうのでしょうか。
その背景には、家族や地域との関係性の希薄化など、様々な社会的要因があります。
そして、仮にその方が在宅介護サービスを利用していたとしても、従来のサービスの仕組みだけでは、24時間の安心を担保するには「限界」があるのもまた事実なのです。
■訪問と訪問の間に生まれる「空白の時間」
週に数回、決まった時間に訪問するスタイルのサービスでは、どうしてもケアが提供されない「空白の時間」が生まれてしまいます。
「今日の夕方ヘルパーさんが帰ったあと、次の訪問は明日の朝…」 この十数時間の間に利用者様の容態が急変してしまったら…。
そう考えると、不安を感じずにはいられません。
■利用者様自身がSOSを出せない現実
もう一つの大きな課題は、いざという時にご本人が助けを呼べないケースが多いということです。
例えば、ベッドから落ちて身動きがとれなくなってしまったり、急な体調不良で電話に手が届かなかったり…
助けを呼びたくても呼べないまま、時間が過ぎていってしまう…こうした悲しい事態は、残念ながら決して少なくありません。
これらの課題は、ケアマネジャーやヘルパー一人ひとりの努力だけでは、なかなか埋めることが難しいのが現実です。
だからこそ、サービスの仕組みそのものから見直していく必要があるのではないでしょうか。
従来のサービスが抱える「空白の時間」を埋め、利用者様の「もしも」に備える、
その大きな可能性を秘めているのが、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(定期巡回・随時対応サービス)」です。
このサービスが、孤立死を防ぐために果たせる3つの大きな役割をご紹介します。
1.短い間隔の訪問で「点」の支援を「線」に変える
定期巡回サービスは、1日に複数回、短い時間でも利用者様のご自宅を訪問し、安否確認やおむつ交換など、その時に必要なケアを行います。
週に数回の訪問という「点」での関わりが、1日複数回の訪問によってつながり、利用者様の1日を「線」で支えることができます。
「何かあってから」対応するのではなく、「今日も変わりない」を確認し続けることが、何よりの安心につながります。
2.24時間つながるコール体制という「お守り」
利用者様は、ケアコール端末などを通じて、24時間365日いつでもオペレーターに助けを求めることができます。
「夜中に胸が苦しくなった」「転んで起き上がれない」 そんな緊急事態にも、すぐに専門のスタッフにつながるという安心感は、ご本人にとって何よりの「お守り」になるはずです。
これは、離れて暮らすご家族の不安を和らげることにも、大きく貢献します。
3.ICT活用で、迅速かつ的確な対応を実現
随時対応の要となるオペレーターは、ICTシステムなどを活用して利用者様の情報をリアルタイムで把握しています。
通報があった際には、その方の基本情報やこれまでのケア履歴などをすぐに確認し、訪問するヘルパーに的確な指示を出すことができます。
情報がしっかりと共有されているからこそ、「誰が」「いつ」「何をするか」が明確になり、迅速で質の高い対応が可能になるのです。
冒頭でご紹介した、自宅で一人亡くなられる方の数は、今の日本が抱える、非常に大きく、そして悲しい現実です。
しかし、私たちはこの現実にただ立ち尽くすわけではありません。
本記事でお伝えしたように、「定期巡回・随時対応サービス」は、利用者様の孤独に寄り添い、24時間365日の安心をお届けできる、大きな可能性を秘めたサービスです。
私たちの仕事は、単なる介護という枠を超え、地域に暮らす方々の命と尊厳を守る、社会にとって不可欠な「セーフティネット」そのものなのです。
とはいえ、この理想的なサービス体制を実際に構築し、日々スムーズに運営していくのは、決して簡単なことではありません。
「オペレーターと訪問ヘルパーの情報連携がうまくいかない…」
「緊急対応の記録や報告書の作成に、どうしても時間がかかってしまう…」
「スタッフの負担が増えてしまい、サービスの質に影響が出ないか心配…」
きっと、多くの事業所様が同じような課題を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
そんな現場の皆様が抱える課題を解決し、もっとスムーズなサービス運営を実現するために開発されたのが、私たちがお届けする定期巡回・随時対応サービス業務支援システム「スマケア」です。
スマケアは、スマートフォン一つで、オペレーターと訪問スタッフ間のリアルタイムな情報共有を可能にし、音声入力による記録作成機能などで、日々の業務負担を大幅に軽減します。
私たちが目指しているのは、ICTの力で現場の業務を効率化し、スタッフの皆様がもっと利用者様と向き合うための「時間」と「心のゆとり」を生み出すことです。
これから定期巡回サービスの導入をご検討中の事業所様も、すでにサービスの運営に課題を感じている事業所様も、 利用者様へのより一層の安心と、スタッフの皆様の働きやすさのために、スマケアがお手伝いできることがあるかもしれません。
一つでも多くの「もしも」を防ぎ、ご本人とご家族に「ここに頼んでよかった」と思っていただくために、まずは情報収集から始めてみませんか?
ご興味のある方は、お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡をお待ちしております。