
【速報】令和8年度「介護職員等処遇改善加算」計画書の提出期限特例まとめ(2/10厚労省通知)

まずは、議論の核心を整理しましょう。
これまで、国の予算編成を担う財務省(財政制度分科会)は、増え続ける社会保障費への対策として、「軽度者へのサービスは専門職の手から離し、ボランティアや地域の助け合い(総合事業)へ移行すべきだ」と強く提言してきました。
「限られた専門職というリソースは、より手厚いケアが必要な中重度者に集中させる」という方針です。
これは財政的な視点で見れば、一つの正論と言えます。
一方、今回の部会において、現場を管轄する厚労省や審議会の委員からは、その実現性に対して慎重な意見が相次ぎました。
「受け皿となる『総合事業』が未整備の地域が多く、サービス難民が生まれかねない」
「専門職の関与がなくなることで、状態悪化(重度化)を招くリスクがある」
「結果として家族の介護負担が増大してしまう」
こうした現場の実情を踏まえ、厚労省は「次期改正で断行するのではなく、引き続き検討を深める」という案を提示し、多くの委員の賛同を得ました。
現場の崩壊を防ぐため、ギリギリのところでブレーキが踏まれた形です。
しかし、ここで重要なのは「財務省が掲げる『給付抑制・効率化』という圧力自体が消えたわけではない」という事実です。
国は今回、「現状では実施困難」と判断しましたが、「持続可能な制度にするために、いずれは構造を変えなければならない」という本音は変わっていません。
つまり、今回の見送り決定は、現状維持を保証するものではなく、私たち事業者に対して「次の改正までの間に、軽度者のみに依存しない強固な経営体質へ転換してください」という猶予期間(ロスタイム)が与えられたと捉えるべきなのです。
「軽度者外しが見送られたなら、当面は安泰だ」
そう思って胸をなでおろしたいところですが、同じ日の審議会でもう一つ、非常にシビアな議論が行われていたことを忘れてはいけません。
それは、「ケアマネジメント(居宅介護支援)への利用者負担の導入」です。
これまでケアプランの作成費用は全額保険給付(利用者負担ゼロ)でしたが、ここにもメスを入れようという議論が具体化しています。
今回の部会で厚労省から提示された「たたき台」には、驚くほど具体的な徴収案が並びました。
●利用者の所得に応じて負担を求める案
●有料老人ホームなどの居住者から徴収する案
●給付管理業務などの事務費用を実費として徴収する案
特に3つ目の「事務費用の徴収」まで議論の遡上に載ったことは、国がいかに「あらゆる手段で給付を適正化(抑制)したいか」という強い意志の表れと言えます。
軽度者の移行こそ一旦保留となりましたが、「財政難」という根本的な問題は何一つ解決していません。
「どこかを削らなければ制度が持たない」という状況の中で、訪問介護や通所介護への風当たりが弱まることはないでしょう。
むしろ、今回の見送りによって、次回(2027年)以降、より抜本的な改革を迫られる可能性すらあります。
では、私たち介護事業者は、与えられた「次の改正までの時間」をどう使うべきでしょうか。
私たちは、「国が予算を投下したがっている分野」へ事業の軸足を移すことが、最も確実な道筋だと考えます。
財務省や厚労省の議論を一貫して読み解くと、一つの共通認識が見えてきます。
それは、「専門職の手は、本当に支援が必要な中重度者のために使うべき」という点です。
軽度者向けのサービスは、今後も報酬単価が上がりにくく、不安定な領域です。
一方で、医療依存度が高い方や、独居で不安を抱える中重度者を支えるサービスは、今後ますますニーズが高まり、国としても報酬を手厚くせざるを得ません。
その「中重度者在宅支援」の切り札となるのが、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(定期巡回)」です。
訪問介護事業者が、今このタイミングで定期巡回へシフト(または併設)するメリットは非常に大きいと言えます。
【定期巡回へシフトする3つのメリット】
●単価と需要の安定: 重度者を支えるサービスのため、報酬単価が高く設定されており、軽度者外しのような制度変更の影響を受けにくい。
●「地域包括ケア」の主役: 頻回訪問と随時対応により、特養待ちの利用者や在宅での看取り希望者を支えることができ、地域での存在感(ブランド力)が増す。
●効率的な人配置員: 移動時間の短縮やICT活用により、訪問介護よりもスタッフ一人当たりの生産性を高めやすい。
今回の「軽度者外し見送り」で得た時間を、今の訪問介護事業を「定期巡回」へ進化させるための準備期間と捉えることこそが、賢い経営判断ではないでしょうか。
「定期巡回の必要性はわかるけれど、24時間対応なんてスタッフが足りない…」
「オペレーションが複雑で、管理しきれるか不安…」
そう感じる経営者様も多いと思います。
確かに、従来のアナログなやり方で定期巡回を始めるのはハードルが高いのが現実です。
そこで不可欠になるのが、ICTの活用です。
私たちが提供する「スマケア」は、まさに定期巡回・随時対応サービスを成功させるために開発されたシステムです。
●リアルタイムの情報共有: 訪問スタッフとオペレーターが瞬時に情報を連携。
●記録業務の自動化: 紙の記録をなくし、直行直帰を可能にすることで、スタッフの移動時間と残業を大幅削減。
●最適なルート作成: 限られた人数で効率よく訪問するためのルートをAIがサポート。
「スマケア」を導入することで、少ない人数でも質の高い24時間ケアを提供することが可能になります。
生産性を上げて利益を出し、それをスタッフの給与に還元する。
この好循環を作ることだけが、これから激化する人材獲得競争を勝ち抜く鍵となります。
2025年11月20日の審議会ニュースは、私たちに「安心」ではなく「準備の時間」を与えてくれました。
「軽度者外し」が見送られた今こそ、目の前の業務に追われるだけでなく、3年後、5年後の未来を見据えた行動を起こすチャンスです。
軽度者中心のモデルから脱却し、中重度者を支える「定期巡回」へのシフトを検討してみませんか?
「スマケア」では、定期巡回の立ち上げから運営ノウハウ、ICT活用による収益改善まで、トータルでご支援しています。
まずは情報収集だけでも構いません。
同業他社がどのような準備を始めているか、資料で確認してみませんか?
定期巡回・随時対応サービスや「スマケア」についてまとめた資料をご用意しました。
ぜひ、下記よりダウンロードしてご覧ください。
ICT活用や「スマケア」の詳細にご興味のある方、定期巡回の開設でお悩みの方は、ぜひ以下お問い合わせフォームより無料でご相談ください。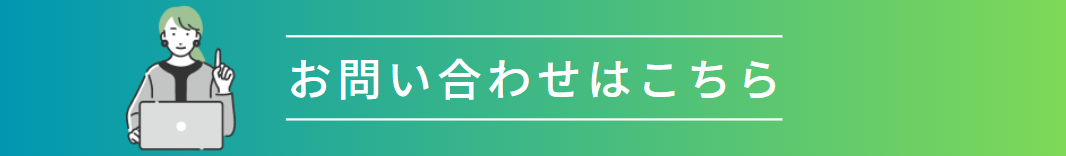
ご興味のある方は、お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡をお待ちしております。