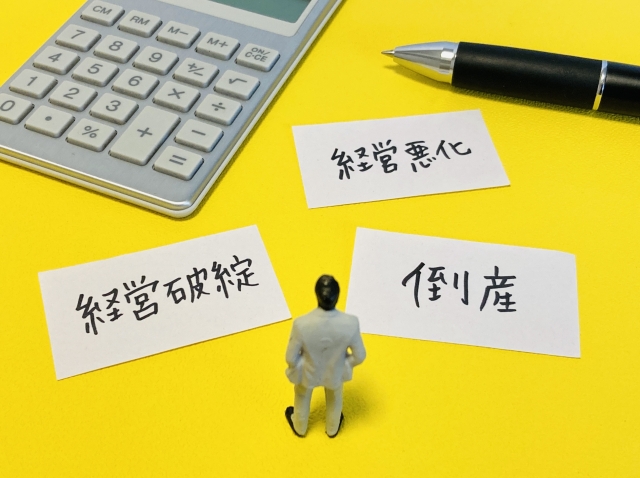
訪問介護の倒産が過去最多。生き残りの鍵は「収支差率No.1」の定期巡回サービスへの転換にあり

毎年11月から2月の冬場にかけて、ノロウイルスによる食中毒が多発しています。
ノロウイルスは、小さな球形をしたウイルスで、非常に強い感染力をもっているのが特徴です。
1件あたりの患者数が多くなる傾向があることから、1年間に発生する食中毒患者数全体の4割以上を占めています。
ここではノロウイルスの症状や感染経路、予防策、特に高齢者にとってのリスクについて説明します。
今回の記事に関連する資料はこちらからダウンロードいただけます!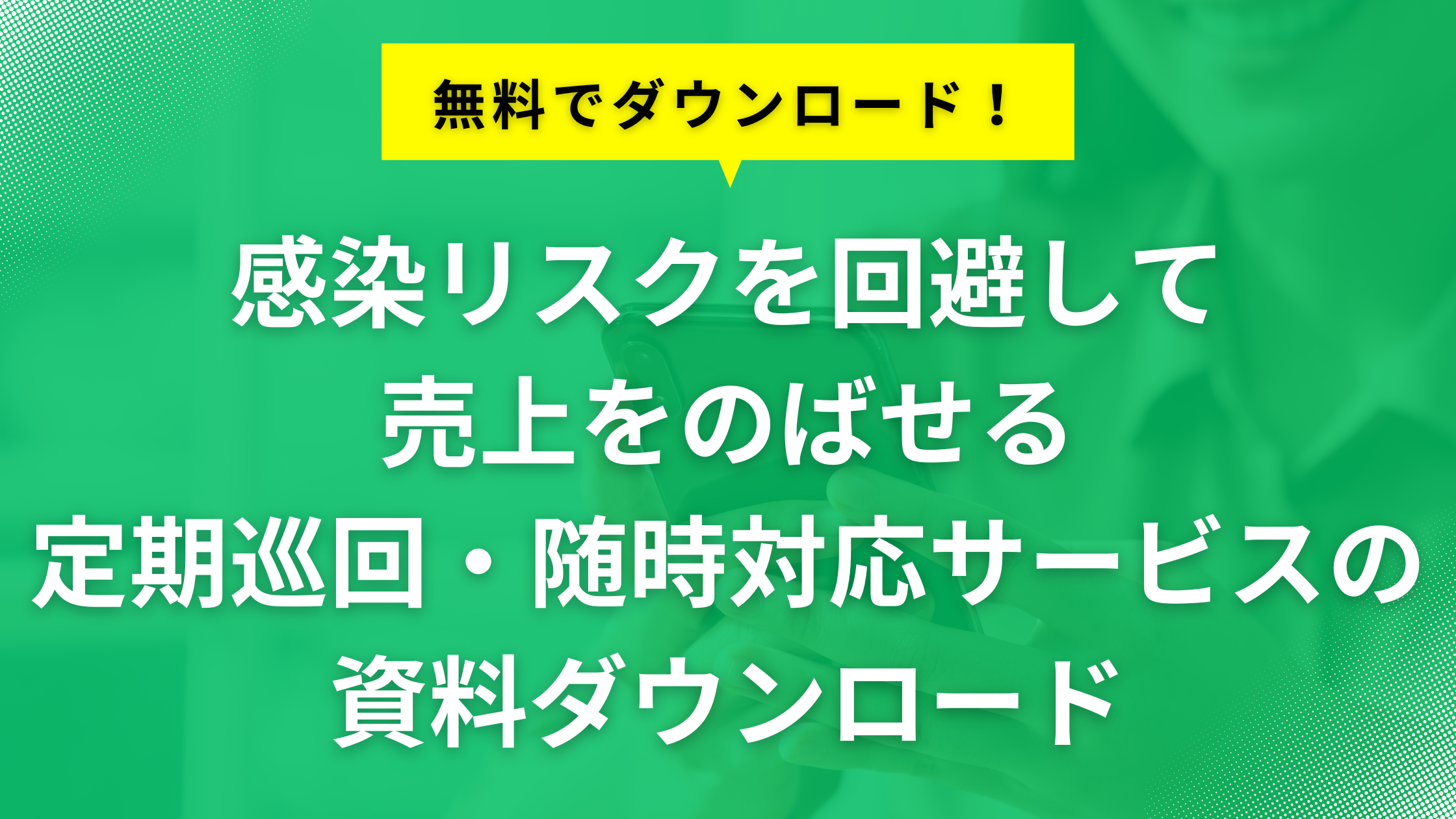

ノロウイルス感染症は、急性胃腸炎を引き起こします。
症状の程度は個人差がありますが、以下のような特徴があります。
(1)主な症状
嘔 吐:特に子どもや高齢者では嘔吐が顕著です。
突然の激しい嘔吐が特徴で、1日に何度も繰り返すことがあります。
下 痢:水様性の下痢が多く、1日に数回から10回以上になることもあります。血便は通常見られません。
腹 痛:胃腸のけいれんや不快感を伴うことがあります。
発 熱:軽度の発熱(37~38℃程度)が見られることがありますが、高熱は稀です。
全身症状:倦怠感、筋肉痛、頭痛など、インフルエンザに似た症状が現れることもあります。
(2)症状の経過
潜 伏 期 間:感染から発症までの期間は通常24~48時間。
症状の持続期間:通常1~3日で改善しますが、体力が低下している人では1週間以上続くこともあります。
回 復 後 :症状が治まった後も、1~2週間程度は便中にウイルスが排出されるため、感染源となる可能性があります。
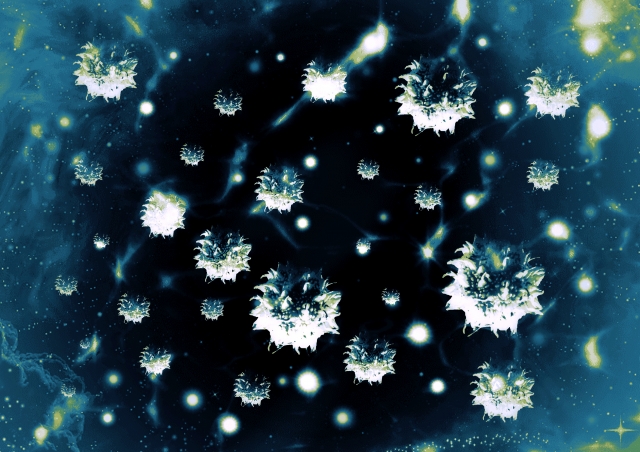
ノロウイルスは非常に感染力が強く、少量のウイルス(10~100個程度)でも感染が成立します。以下は主な感染経路です。
(1)食品を介した感染
◎汚染された食品
特に生牡蠣や二枚貝が原因となることが多いです。
これらの貝類は、海水中のノロウイルスを濾過して体内に蓄積するため、十分に加熱されていない場合に感染リスクが高まります。
◎調理者からの汚染
感染者が調理した食品を介してウイルスが広がることがあります。
(2)接触感染
感染者の嘔吐物や便に触れた手で口に触れることで感染します。
感染者が触れたドアノブ、手すり、スイッチ、タオルなどの物品を介して感染することもあります。
(3)飛沫感染
感染者の嘔吐物や便から発生した微細な飛沫を吸い込むことで感染することがあります。
嘔吐物の処理が不適切な場合、空気中にウイルスが拡散し、周囲の人に感染するリスクがあります。
(4)水を介した感染
汚染された井戸水や飲料水を摂取することで感染することがあります。

ノロウイルスは完全に防ぐことが難しいですが、以下の対策を徹底することで感染リスクを大幅に減らすことができます。
(1)手洗いの徹底
正しい手洗い方法:石鹸を使い、流水で20秒以上手を洗う。指の間、爪の間、手首までしっかり洗う。
洗った後は清潔なタオルやペーパータオルで乾かす。
タイミング:食事前、調理前、トイレの後、嘔吐物や便の処理後
(2)食品の取り扱い
加熱調理:ノロウイルスは85~90℃で90秒以上の加熱で死滅します。
特に二枚貝(牡蠣など)は中心部まで十分に加熱することが重要です。
生食の注意:生牡蠣や加熱不十分な食品の摂取を避ける。
(3)環境の消毒
消毒剤の使用:次亜塩素酸ナトリウム(家庭用漂白剤)を0.1~0.5%に希釈して使用。
アルコール消毒はノロウイルスには効果が限定的です。
嘔吐物や便の処理:使い捨て手袋とマスクを着用し、ペーパータオルで拭き取る。
汚染された場所を次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。汚染された衣類やリネン類は熱湯で洗濯する。
(4)感染者との接触を避ける
感染者がいる場合、嘔吐物や便の処理を適切に行い、感染拡大を防ぐ。感染者が使用した食器やタオルは分けて使用する。

高齢者はノロウイルス感染による影響を特に受けやすいです。
以下にその理由と具体的なリスクを詳しく説明します。
(1)高齢者が感染しやすい理由
免疫力の低下:加齢に伴い免疫機能が低下し、感染症に対する抵抗力が弱まります。
基礎疾患の影響:心疾患、糖尿病、腎疾患などの持病がある場合、ノロウイルス感染がこれらの疾患を悪化させる可能性があります。
集 団 生 活:高齢者施設や病院などでは、感染が広がりやすい環境にあるため、リスクが高まります。
(2)高齢者に特有のリスク
脱水症状:嘔吐や下痢による水分と電解質の喪失が進行しやすい。
脱水が進むと、意識障害や腎不全などの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。
誤嚥性肺炎:嘔吐物を誤って気道に吸い込むことで、肺炎を引き起こすリスクがあります。
栄養不良:食欲不振や消化不良により、栄養状態が悪化することがあります。
(3)高齢者への対応
早期の医療介入:高齢者が感染した場合、早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが重要です。
水 分 補 給:経口補水液(ORS)やスポーツドリンクを用いて、こまめに水分と電解質を補給する。
感染予防の徹底:高齢者施設では、感染者を隔離し、職員や他の入居者への感染拡大を防ぐ。

ノロウイルスに特効薬はありません。対症療法(脱水予防、電解質補正など)が中心となります。
また、現時点ではノロウイルスのワクチンは実用化されていません。
学校、病院、介護施設などでは、1人の感染者から集団感染が発生することがあるため、迅速な対応が求められます。

定期巡回・随時対応サービスは、1日に複数回のサービス提供を行うので、その都度便や嘔吐を処理したり、水分補給を促したり、利用者の状態に応じて柔軟に対応できます。
また、利用者からの通報で緊急時には駆けつけるので、急な体調変化にも素早く対応することができます。
利用者が通うデイサービスなどでノロウイルスが発生した際も、自宅待機する利用者にサービス提供できるので、集団感染のリスクを回避しつつ、自宅での生活を継続できます。
定期巡回・随応サービス業務支援システム「スマケア」を導入いただければ、サービス提供記録や利用者のバイタルなどの情報をケアマネジャーや看護師、主治医などの関係者間で瞬時に共有できます。多職種間で利用者の状態を把握できるので、そのときの状況に応じたより適切なサービスを提供できるようになります。
また、通話内容を自動的に録音したり、通報時間を自動的に記録したりできるので、緊急時のオペレーターの対応についても後日確認することができます。
スマケアに関するお問い合わせはこちら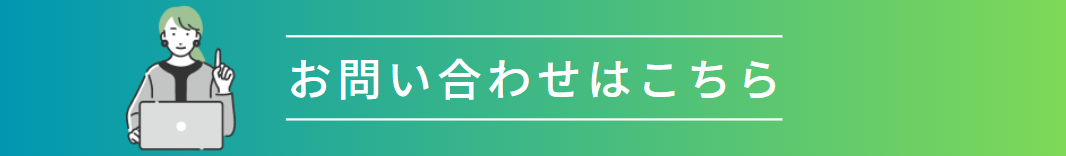
ノロウイルスは非常に感染力が強い一方で、基本的な予防策を徹底することで感染リスクを大幅に減らすことが可能です。
特に高齢者や免疫力が低下している人々に対しては、早期の対応と適切なケアが重要です。
定期巡回・随応サービスを利用し、且つスマケアを導入いただければ、迅速に対応することができます。
ご興味のある方は、下記お問い合わせフォームよりご連絡をお待ちしております。