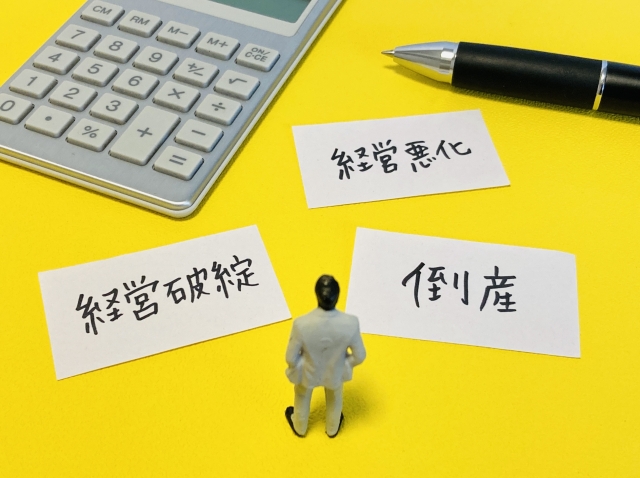
訪問介護の倒産が過去最多。生き残りの鍵は「収支差率No.1」の定期巡回サービスへの転換にあり

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下、定期巡回・随時対応サービス)は、利用者の自宅での生活を支えるために、介護職員や看護師が連携してサービスを提供します。
また、ケアマネジャー、医師、他の介護事業者など、様々な専門職が関与します。
それぞれの職種が持つ専門性を活かしながら、利用者に最適なケアを提供するためには、情報共有が不可欠です。
ここでは、定期巡回・随時対応サービスおける多職種間の情報共有の大切さを説明します。
今回の記事に関連する資料はこちらからダウンロードいただけます!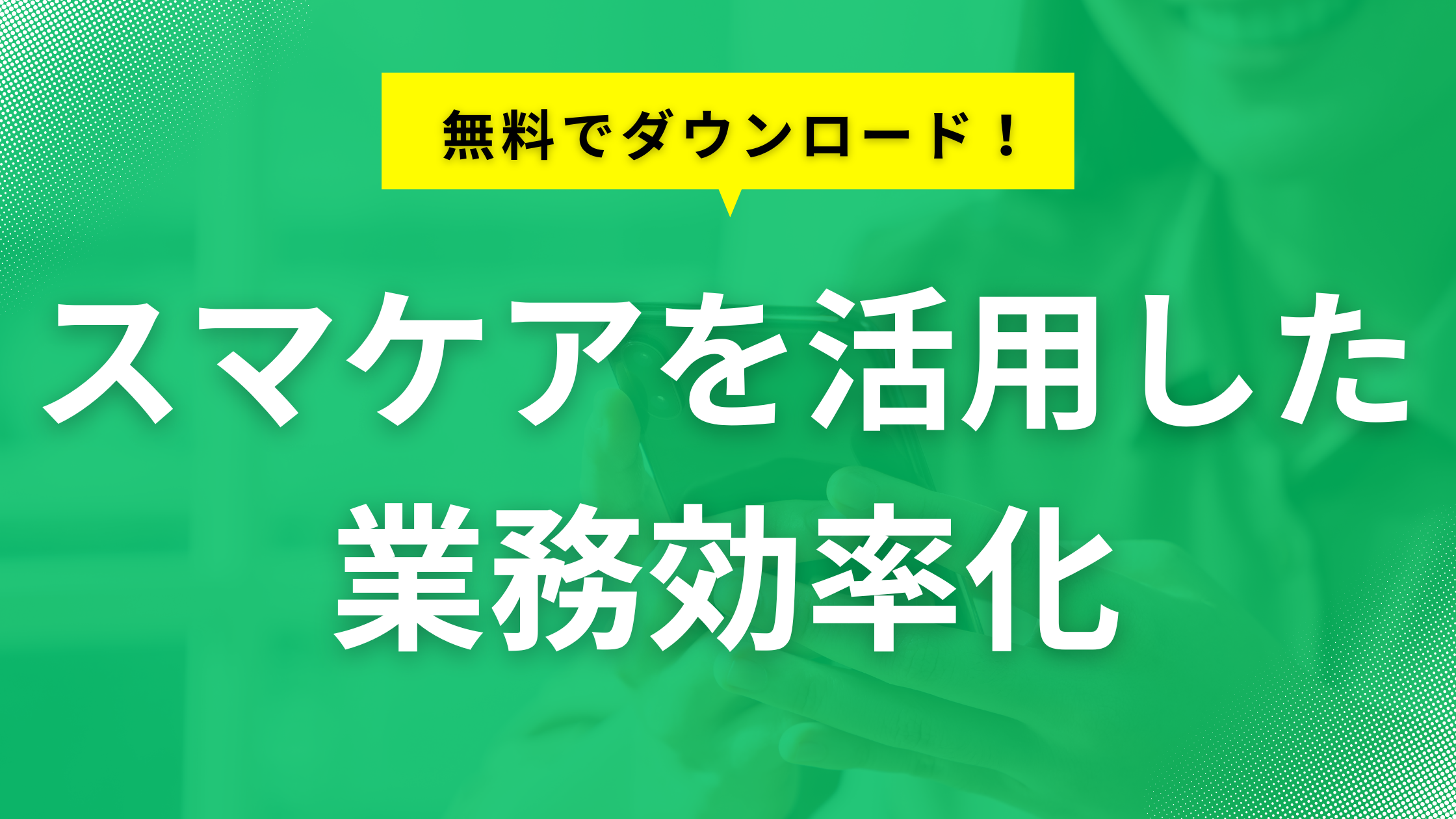

利用者の状態は、日々、時には時間単位で変化します。
特に高齢者や持病を抱える方の場合、体調の変化が急激であることも少なくありません。
以下のような情報を多職種間で共有することで、利用者の状態を正確に把握できます。
◊健康状態
血圧、体温、脈拍、呼吸状態、食欲、睡眠状況など
◊生活状況
食事の摂取量、排泄状況、入浴や着替えの状況、家事の実施状況など
◊精神状態
不安やストレス、認知症の進行具合、感情の変化など
◊環境要因
自宅の安全性、家族のサポート状況、近隣との関係など
例えば、介護職員が「最近、利用者が食事を残すことが多い」と気づいた場合、その情報を看護師や医師などに共有することで、体調不良や栄養不足のリスクを早期に察知し、適切な対応を取ることができます。
2.迅速かつ適切な対応を行うため

定期巡回・随時対応型のサービスでは、利用者の緊急事態に対応することが求められます。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
◊急な体調不良
発熱、呼吸困難、意識障害など
◊転倒や怪我
自宅内での転倒や外傷など
◊精神的な不安定
認知症による混乱や不安の増大など
これらの状況において、迅速かつ適切な対応を行うためには、事前に利用者の既往歴、服薬状況、アレルギー情報、緊急連絡先などを多職種間で共有しておくことが重要です。
また、緊急時には、介護職員が現場で得た情報を看護師や医師に即座に伝えることで、適切な指示を仰ぐことができます。
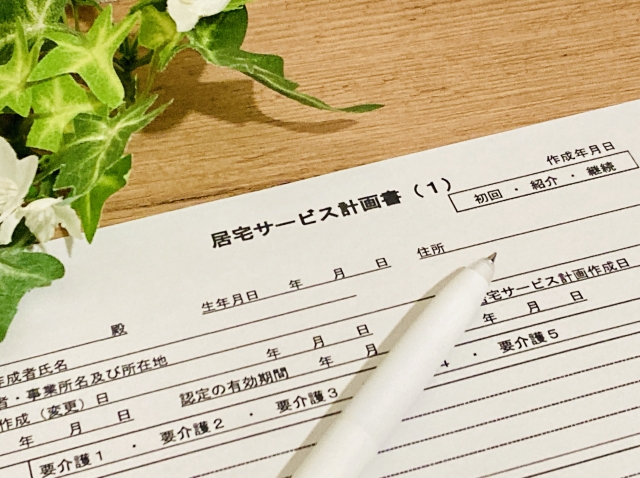
多職種が連携して情報を共有することで、利用者に対するケアプランをより効果的に調整できます。
具体的には以下のような場面で役立ちます。
◊ケアプランの見直し
ケアマネジャーが利用者の最新の状態を把握し、必要に応じてケアプランを変更する
◊服薬管理
介護員が利用者の服薬状況を確認し、看護師や医師と連携して適切な服薬管理を行う
例えば、介護職員が「利用者の足のむくみがひどくなっている」と報告した場合、医師が利尿剤の処方を検討し、看護師やリハビリ職がむくみを軽減するための運動を提案する、といった連携が可能になります。

利用者やその家族にとって、多職種が一丸となって支援しているという安心感は非常に重要です。
情報共有が適切に行われていると、以下のようなメリットがあります。
◊一貫性のあるケア
どの職種が関わっても、同じ方針でケアが提供される
◊家族への説明がスムーズ
家族からの質問や不安に対して、チーム全体で一貫した回答ができる
◊信頼関係の構築
利用者や家族が「自分たちの状況をしっかり把握してくれている」と感じることで、信頼が深まる
例えば、家族が「最近、母が夜中に何度も起きるようになった」と相談した場合、介護職員がその情報をケアマネジャーや計画作成責任者に共有し、原因を探るための対応を迅速に行うことができます。

情報共有が不十分だと、以下のような問題が発生する可能性があります。
◊重複した対応
同じ内容を複数の職種が確認する
◊対応の遅れ
必要な情報が伝わらず、対応が後手に回る
◊ミスの発生
情報の伝達ミスにより、誤った対応が行われる
これを防ぐために、情報共有の仕組みを整えることが重要です。
例えば、ICT(情報通信技術)を活用して、訪問記録やケアプランをリアルタイムで共有することで、業務の効率化が図れます。

多職種が連携して働くためには、信頼関係が不可欠です。
情報共有は、以下のような形で信頼関係の構築に寄与します。
◊お互いの専門性を尊重
各職種が持つ専門知識やスキルを共有し合うことで、相互理解が深まる
◊コミュニケーションの活性化
定期的な情報共有を通じて、チーム内のコミュニケーションが円滑になる
◊問題解決能力の向上
チーム全体で情報を共有し、協力して問題に対処することで、より良い結果を生み出す
例えば、看護師が「利用者の血圧が高い」と報告した際に、介護職員が「最近、塩分の多い食事を好むようになった」と補足することで、ケアマネジャーや計画作成責任者が適切なケアプランを提案できるようになります。

情報共有を効果的に行うためには、以下のような方法が考えられます。
◊定期的なカンファレンス
チーム全体で利用者の状況を共有し、ケアプランを見直す
◊訪問記録の共有
訪問時の記録を電子化し、リアルタイムで共有する
◊ICTの活用
スマートフォンやタブレットを活用して、情報を迅速に共有する
◊緊急時の連絡体制
緊急時に迅速に情報を伝達できる体制を整える
◊家族との連携
家族からの情報も積極的に収集し、チーム内で共有する
定期巡回・随時対応サービスにおける多職種との情報共有は、利用者の安全・安心を守り、ケアの質を向上させるために欠かせない要素です。
情報共有を通じて利用者の状態を正確に把握し、迅速かつ適切な対応を行い、ケアの質を高めることができます。
また、利用者や家族の安心感を高め、業務の効率化や多職種間の信頼関係の構築にも寄与します。
チーム全体で情報共有の重要性を認識し、適切な仕組みを整えることが重要です。
定期巡回・随時対応サービス業務支援システム「スマケア」を導入することで、サービスの提供記録やバイタルなどを瞬時に関係者や利用者(その家族)に情報共有することができます。
緊急時の対応をサービス内容に含む定期巡回・随時対応サービスにおいて、多職種とのリアルタイムでの情報共有は必須です。
定期巡回・随時対応サービスを開設している、または開設を検討している方は、ぜひスマケアの導入をご検討ください。
ご興味のある方は、お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡をお待ちしております。