
【2026年6月処遇改善加算改定】定期巡回サービスが「加算率27.8%」を勝ち取る方法

日本の介護が、今まさに大きな岐路に立たされています。
急速な高齢化と、担い手となる生産年齢人口の減少。
この二重の課題は「2040年問題」とも呼ばれ、介護サービスの持続可能性が国家的な課題となっています。
先日開催された第127回社会保障審議会介護保険部会では、この深刻な現実と、それを乗り越えるための具体的な戦略が議論されました。
今回はその要点を分かりやすく解説し、日本の介護が目指す未来像を探ります。
「定期巡回サービスについて知りたい、興味がある」という方は
まずはこちらの資料を無料でご確認ください!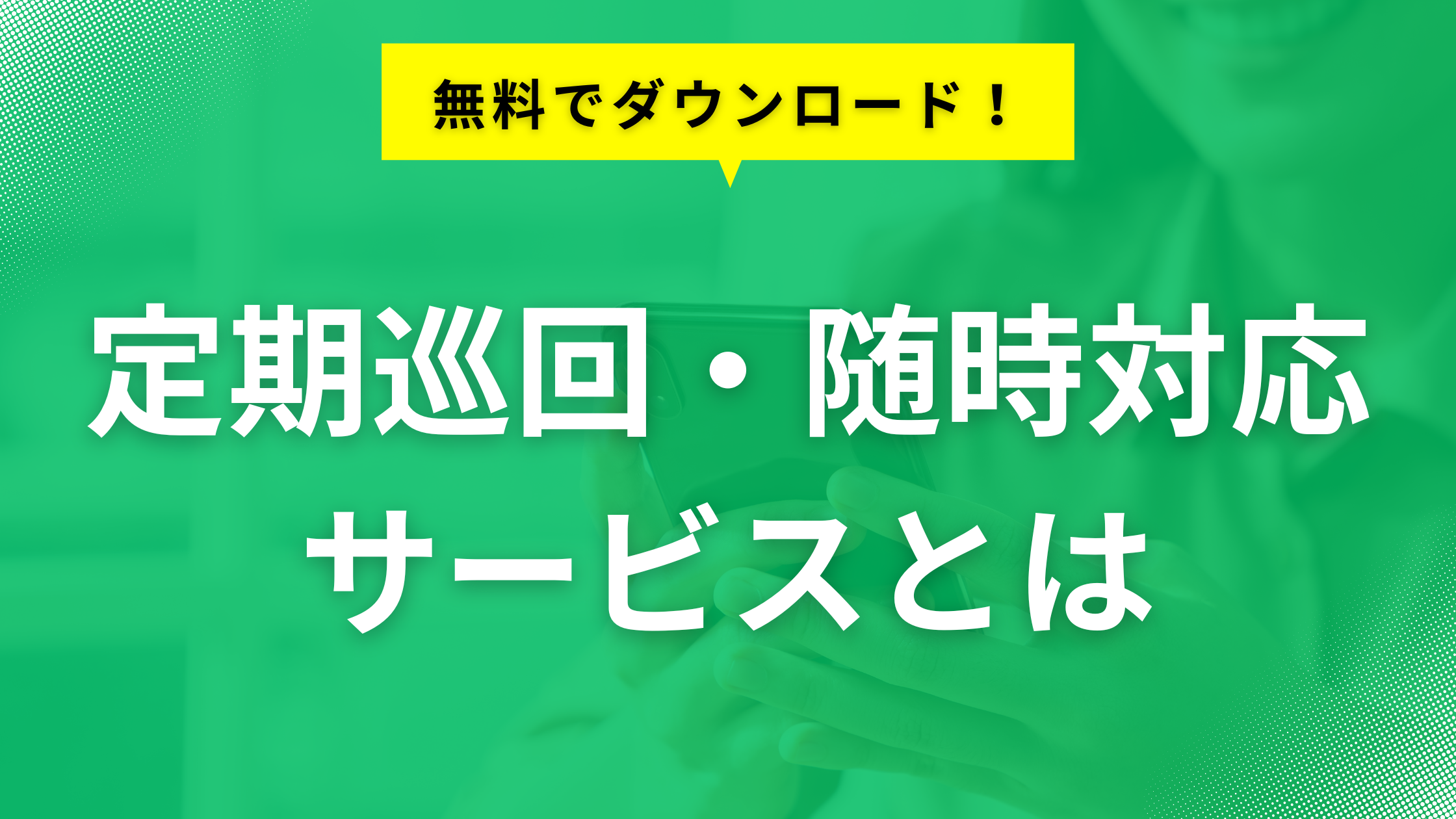
◆参考資料
令和7年10月27日 社会保障審議会介護保険部会(第127回)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html
まず直視すべきは、深刻な人材不足です。
国の推計によれば、2040年度には約272万人の介護職員が必要とされています。
これは、新たにおよそ57万人の担い手を確保しなければならない計算です。
さらに衝撃的なことに、直近の統計では介護職員数が初めて「減少」に転じました。
需要が増え続ける一方で、供給が追いつかないどころか減り始めているのです。
この危機的状況に対し、国は「人材確保」と「業務の効率化」を両輪で進める戦略を打ち出しています。
限られた人材で質の高いサービスを維持・向上させるため、国は「2040年までに介護分野全体で20%の業務効率化」という高い目標を掲げました。
これは、単なるコストカットではありません。
「職員の負担を減らし、生まれた時間でケアの質を高める」ことが目的です。
その具体的な中身を見てみましょう。
1.テクノロジーのフル活用(介護ロボット・ICT・AI)
見守り支援機器による夜間の訪問の最適化、介護記録ソフトやAIによる事務作業の自動化・効率化など、テクノロジー導入が加速します。
これにより、職員が書類作業に追われる時間を大幅に削減します。
2.「介護助手」によるタスクシフト
介護職員が、専門性を要する直接的なケアに集中できるよう、清掃、配膳、ベッドメイキングといった周辺業務を「介護助手」が担う取り組みが推進されています。
すでに約半数の事業所が導入しており、職員の負担軽減とケアの質向上に繋がっています。
3.データに基づく科学的介護「LIFE」
利用者の状態やケア内容のデータを集約・分析する「LIFE」システムを活用し、エビデンスに基づいたPDCAサイクルを回すことで、ケアの質そのものを向上させます。
これらの取り組みを地域全体で進めるため、全都道府県に「介護生産性向上総合相談センター」の設置が進められており、事業者を強力にバックアップする体制が整いつつあります。
制度を未来にわたって維持するため、聖域なき議論も進められています。
1.ケアマネジャーの負担軽減
制度の要であるケアマネジャーも、従事者数が伸び悩んでいます。
その原因の一つが、利用者宅への訪問やケアプラン作成といった本来業務に加え、「入院時の付き添い」や「行政手続き支援」といった法定外の業務負担です。
このため、事業者間で情報をスムーズにやり取りできる「ケアプランデータ連携システム」の普及や、研修時間の短縮・柔軟化、さらには受験資格の見直し(例:救急救命士などを対象に加える)などが検討されています。
2.給付と負担の公平性
保険制度を維持するため、「給付と負担」の見直しも重要な論点です。
✓ ケアマネジメントへの利用者負担導入(現在は全額保険給付)
✓ 軽度者(要介護1・2)の生活援助サービスを、市町村の総合事業へ移行
✓ 介護老人保健施設(老健)などの多床室の室料負担の見直し
これらは利用者の負担増に直結する可能性もあり、慎重な議論が重ねられていますが、第10期介護保険事業計画(2027年度開始)までには結論が出される見通しです。
ここまで見てきた「人材不足」「生産性向上」「ICT活用」「ケアマネ負担軽減」というキーワードは、すべて「地域で高齢者の生活を支え続ける」という目的に集約されます。
そして、これらの課題解決と非常に親和性が高いサービスが、すでにあることをご存知でしょうか。
それが「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」サービスです。
◇定期巡回サービスの特徴
1.1日複数回の「定期訪問」(短時間のケアや安否確認)
2.緊急時に通報できる「随時対応」(オペレーター対応)
3.通報を受けて駆けつける「随時訪問」
これらを24時間365日体制で組み合わせ、在宅生活をトータルで支えるものです。
今回の審議会で議論された「生産性向上」の方向性と、定期巡回サービスはまさしく合致しています。
◇ICT活用の先進性
オペレーターシステムやタブレット端末での記録・情報共有が前提であり、ICT活用による効率化が組み込まれています。
◇人材の効率的活用
短時間の訪問を柔軟に組み合わせることで、限られた人材で多くの利用者のニーズにきめ細かく応えられます。
◇ケアマネとの連携強化
データ連携が進めば、ケアマネジャーは利用者の日々の状態変化(サービス提供記録やオペレーターへの通報履歴など)をリアルタイムで把握でき、より精度の高いケアプラン作成に集中できます。
介護人材が減少し、テクノロジー活用が必須となるこれからの時代において、定期巡回・随時対応サービスは、軽度者から重度者まで、多くの高齢者が住み慣れた自宅で安心して暮らし続けるための「切り札」となり得ます。
今回の審議会の議論は、こうした先進的なサービスがより普及・促進されるべきであると、強く後押しするものと言えるでしょう。
日本の介護の未来は決して楽観できませんが、課題が明確になった今、官民一体となった改革が始まっています。
ICT活用や「スマケア」の詳細にご興味のある方、定期巡回の開設でお悩みの方は、ぜひ以下お問い合わせフォームより無料でご相談ください。
ご興味のある方は、お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡をお待ちしております。