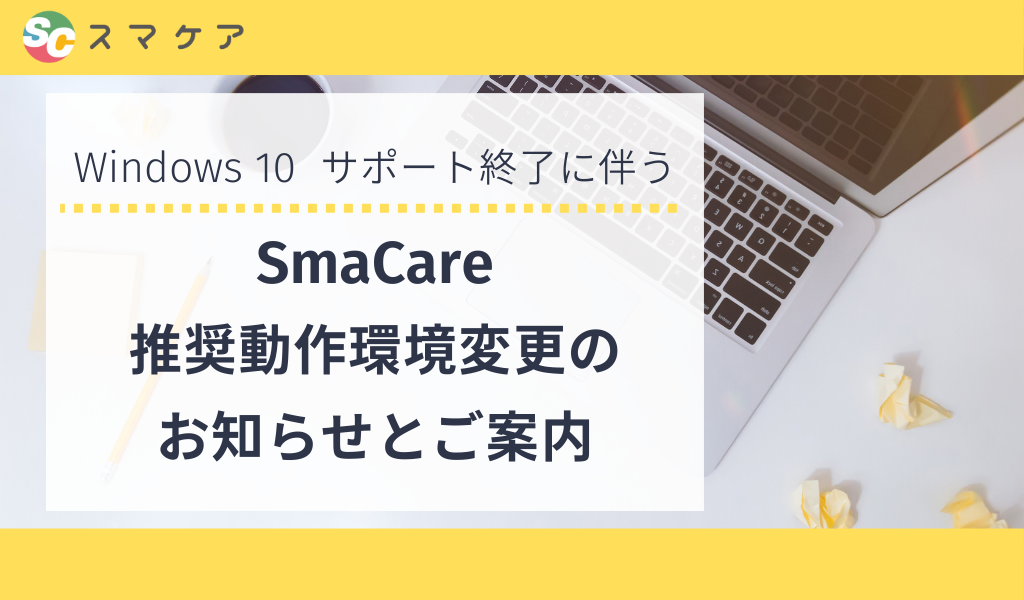
【Windows10サポート終了】SmaCare推奨動作環境変更のお知らせとご案内

令和6年5月21日に開催された財政制度等審議会(以下、財政審)の財政制度分科会において、資料「我が国の財政運営の進むべき方向(案)」が提示され、介護分野については以下の項目が示されました。
「我が国の財政運営の進むべき方向(案)」はこちら
|
①生産性の向上 ②高齢者向け施設・住まいにおけるサービス提供の在り方 ⑥生活援助サービスに関するケアプラン検証の見直し |
以下、各項目について内容を要約してお伝えします。
①生産性の向上
ア)ICT機器を活用した人員配置の効率化
日本全体で労働力不足が課題となっており、特に介護分野での人材確保が喫緊の課題となっています。
介護ニーズの増大に対応するためには、介護現場でのタスク・シフト/シェアの推進に加え、ICT 機器の活用による人員配置の効率化が不可欠です。
2024年度の介護報酬改定では、特定施設や介護老人保健施設での人員配置基準の柔軟化が行われました。
今後も ICT 機器の導入・活用を推進しつつ、特別養護老人ホームや通所介護などでの人員配置基準の更なる柔軟化を実施すべきです。
これにより、限られた介護人材を有効に活用し、生産性の向上を図ることで、増大する介護ニーズに対応していくことが重要です。
イ)経営の協働化・大規模化の推進
介護の生産性向上には、経営の協働化や大規模化が重要な取り組みです。
在宅・施設ともに、規模が大きいほど収支差率が良好となっている。特に営利法人の収支差率が社会福祉法人よりも良好です。
そのため、規模の利益を活かして業務効率化や職場環境改善を図るため、経営の協働化・大規模化を早急に進めるべきである。補正予算で支援策も用意されています。
介護事業者の休廃業件数は増加しているが、営利法人の新規参入も多いです。一方、社会福祉法人の新規設立・解散・合併は少ない状況にあります。
社会福祉法人の多くは小規模であり、利益率が低調だが、規模が大きいほど労働生産性や給与水準が高くなる傾向にあります。
今後は特に社会福祉法人における経営の協働化・大規模化を円滑に進める環境整備を図るべきです。
②高齢者向け施設・住まいにおけるサービス提供の在り方
ア)高齢者向け施設・住まいの整備の在り方
高齢者向け施設・住まいには、特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、住宅型有料老人ホーム等があります。
特別養護老人ホームの入所者が要介護度3以上に限定されたことから、介護付き有料老人ホームやサ高住などの整備が進められてきました。
住宅型有料老人ホームやサ高住においても要介護度3以上の入居者が3~5割を占めるようになっており、一部は特養と同等の機能を持ちます。
一方で、住宅型有料老人ホームやサ高住は介護保険事業計画の任意記載事項であり、総量規制の対象外となっています。
そのため、介護保険施設と非指定の高齢者向け住まいの役割分担を改めて検討し、地方自治体の介護保険事業計画において、有料老人ホームやサ高住も含めた高齢者向け住まいの整備方針を明確に位置づける必要があります。
地域包括ケアの推進の観点から、有料老人ホームやサ高住における要介護者のサービス需給も勘案した一体的な整備方針を定めるべきです。
イ)利用者に対する囲い込み等への対応
有料老人ホームやサ高住の事業者は、自ら介護サービスを提供するよりも、関連法人が外付けで介護サービスを提供した方が、より多くの介護報酬を得られるという構造があります。
これにより、未届けの施設を含めた利用者の囲い込み・過剰サービスの原因となっています。
自ら介護サービスを提供する施設よりも、外付けで介護サービスを活用する施設の方が家賃等が安い傾向にあります。安い入居者負担で利用者を囲い込み、関連法人による外付けサービスを活用した介護報酬で利益を上げるビジネスモデルが成立しています。
このため、有料老人ホームやサ高住における利用者の囲い込みの問題に対しては、個別の対応策ではなく、外付けの介護サービスを活用する場合も、区分支給限度基準額ではなく特定施設入居者生活介護(一般型)の報酬を上限とする形で、介護報酬の仕組みを見直すべきです。
③保険外サービスの活用
増大する多様な介護需要に対して、介護保険事業と介護保険外の民間サービスを組み合わせることが有効です。
介護保険事業者が保険内外のサービスを柔軟に提供することで、高齢者のニーズに応え、事業者の効率的なサービス提供や収益の多様化、経営基盤の強化が可能となる。また、これにより職員の賃上げにも還元できます。
現在、利用者保護や保険給付の適正化のため、サービスの区分や説明責任の明確化などのルールがあるものの、地方公共団体によってはそれらのルールの解釈が異なり、保険外サービスが認められない(ローカルルール)という声があります。
そのため、ローカルルールの実態を把握した上で、国民の利便性向上の観点から、介護保険外サービスの柔軟な運用を認めるべきです。
④人材紹介会社の規制強化
介護事業者が人材紹介会社を活用して人材を採用する際、一部の人手不足事業者は高額な手数料を支払っている状況にあります。
人材紹介会社経由の場合、離職率が高いとの調査もあり、必ずしも安定的な職員確保につながっているとは言えません。
介護職員の給与は公費と保険料を財源としており、本来は職員の処遇改善に充てられるべきものの、割高な手数料の支払いに回っている現状は問題があります。
そのため、人材紹介会社に対する指導監督の強化、一定期間内の離職者に対する手数料返金の検討など、実効性ある対策を講じるべきです。
また、ハローワークや都道府県などによる公的人材紹介サービスの充実化も図るべきです。
⑤軽度者に対する生活援助サービス等の地域支援事業への移行
介護サービスの需要が大幅に増加する一方で、介護の人材や財源に限りがあります。
そのため、全国一律の基準ではなく、地域の実情に合わせた人員配置や運営基準の緩和等を通じて、多様な人材や資源の活用を図り、必要なサービスを提供する枠組みを構築する必要があります。
具体的には、要介護度の高い方への給付を重点化し、軽度者(要介護1・2)に対する訪問介護・通所介護についても、段階的に地域支援事業への移行を目指すべきであります。
そうすることで、生活援助型サービスなど、地域の実情に合わせた多様な主体による効果的・効率的なサービス提供を可能にすることができます。
⑥生活援助サービスに関するケアプラン検証の見直し
利用回数の多い訪問介護の生活援助サービスについては、2018年10月より、ケアプランの保険者への届出が義務化され、保険者による点検や地域ケア会議での検証が行われることとなりました。
しかし、届出を避けるため、生活援助サービスから身体介護サービスへの振替が行われているとの指摘があります。また、ケアプラン検証の取り組みには地方公共団体による差があります。
そのため、身体介護への振替を是正し、訪問介護全体での適切なサービスを確保するため、身体介護も含めた訪問介護全体の回数での届出を義務付けるなど、制度の更なる改善が必要です。
また、各地方公共団体のケアプラン検証の取り組み状況を定期的に把握し、より実効的な点検を行うことで、必要なサービスの確保と適正化を図るべきです。
(2)給付の在り方(ケアマネジメントの利用者負担の導入)
介護保険サービスの利用には一定の利用者負担があるが、居宅介護支援(ケアマネジメント)については制度創設時から利用者負担がない取り扱いとされてきました。
介護保険制度創設から20年以上が経ち、ケアマネジメントの利用は定着しているが、現役世代の保険料でケアマネジメントの費用を肩代わりし続けることは世代間の公平性の観点から問題があります。
また、利用者負担がないことで、利用者側からケアマネジャーの業務の質に対するチェックが働きにくい構造となっています。
利用者自身がケアプランに関心を持つことで、サービスの質の向上につながると考えられます。
公正・中立なケアマネジメントを確保するために、質の評価手法の確立や報酬への反映と共に、居宅介護支援に利用者負担を導入することで、質の高いケアマネジメントが選ばれる仕組みを構築する必要があります。
(3)負担の在り方
①利用者負担の見直し
介護保険の利用者負担については、2割負担の対象者範囲拡大について検討されてきたが、結論は令和9年度からの次期事業計画開始までに出すこととされました。
昨年の議論では主に収支への影響が中心で、利用者の金融資産等を勘案した議論は十分ではなかった。一方で、利用者負担見直しを行わないと介護保険料の上昇による影響が生じています。
そのため、負担能力に応じた公平な制度設計の観点から、金融資産等の反映も含めて早急に2割負担の対象者範囲拡大を実現すべきです。
また、医療保険と同様に、利用者負担を原則2割とすることや、現役世代並み所得(3割)等の判断基準の見直しについても検討すべきです。
②多床室の室料負担の見直し
介護老人保健施設と介護医療院の多床室については、その室料相当分が介護保険給付の基本サービス費に含まれたままとなっています。
2024年度の介護報酬改定では、一部の施設で新たに室料負担が導入されたものの、その対象は全体の一部にすぎないです。
一方で、これらの施設は利用者にとって「生活の場」となっている実態があります。居宅と施設の公平性の観点から課題が残されています。
したがって、今回見送りとなった残りの施設についても、多床室の室料相当額を基本サービス費から除外する見直しを更に行うべきです。
まとめ
財政審を運営する財務省は、他省庁の予算を査定する官庁で、これまでも年々増加する社会保障費(医療・介護・年金等)について、財政審等を通じて厳しい提言をしてきました。
今回、財政審で示された案にも、介護事業者の経営に大きな影響を与えるものがあり、なかでも、「高齢者向け施設・住まいの整備の在り方」は、サ高住や住宅型有料の総量規制、「利用者に対する囲い込み等への対応」は、サ高住や住宅型有料の特養の報酬を上限とすることが示されており、これまでの「集合住宅を各地に増やし、区分支給限度額いっぱいまで訪問介護や通所介護等の介護保険サービスを利用する」ような、ビジネスモデルからの転換を促すものになります。
上記の流れをふまえながら、限られた経営資源のなかで、「介護の質」を担保しつつ、効率的に経営を行うには、月額包括報酬である定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の地域密着型サービスを導入するといった方法が考えられます。
一方で、財務省や財政審の意見がそのまま国の予算案に反映されるわけでもなく、各省庁や団体等の意見を調整・反映し、より現実的な案としてまとめ上げられます。今後の議論の推移を注視し、状況に応じていち早く対応することが肝心です。
その他、定期巡回に係わる様々なトピックスや、お役立ち情報をメルマガにて発信を予定しております。
ご興味のある方は こちら よりご登録ください。
ご不明点等ございましたら
ホームネット株式会社 スマケアサポートデスクへ
TEL 050-1807-1917(平日 9:00〜18:00)![]() お問合せは こちら
お問合せは こちら